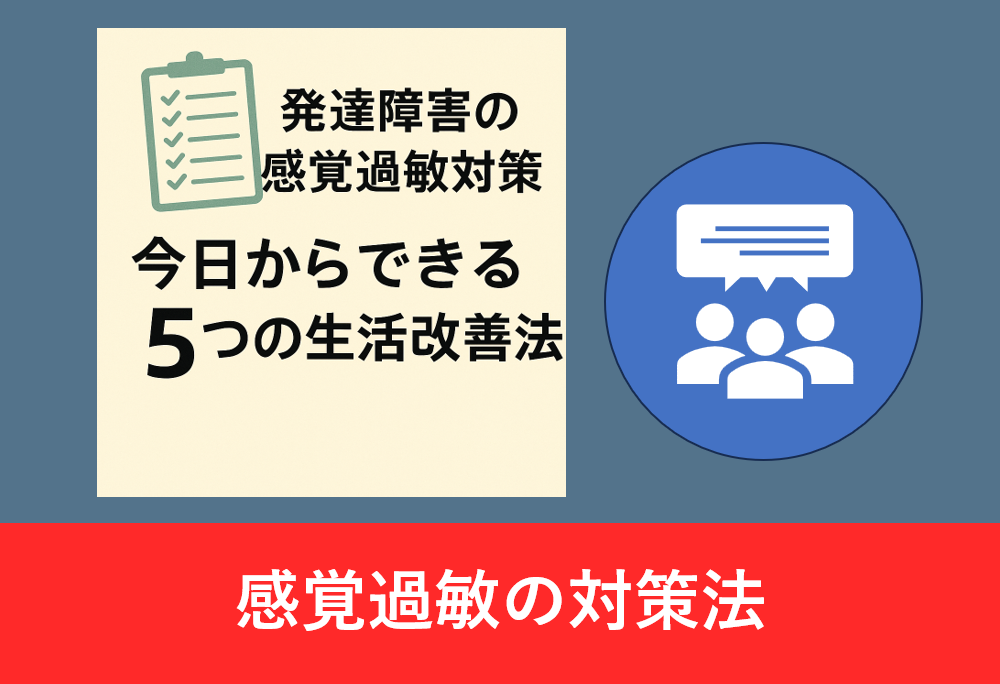発達障害を持つ方の中には、音・光・匂い・触覚などに対して過敏に反応してしまう「感覚過敏」に悩まされている方が少なくありません。日常生活の中で「普通のこと」が苦痛になることもあり、周囲の理解が得られにくいこともあります。
この記事では、感覚過敏の特徴と原因を整理したうえで、今日から実践できる5つの生活改善法を紹介します。ご本人はもちろん、支援者や家族の方にも役立つ内容です。
感覚過敏とは?
発達障害と感覚過敏の関係
発達障害(ASD、ADHD、LDなど)を持つ方の中には、感覚の受け取り方が一般的な人と異なるケースがあります。特定の刺激に対して過剰に反応してしまう「感覚過敏」は、生活の質に大きく影響します。
主な感覚過敏の種類
 支援員
支援員日々支援してきた中で、感覚過敏の方でも特に苦手な部分は人によって違いました。
| 間隔の種類 | 過敏の例 |
|---|---|
| 聴覚 | 時計の秒針音や換気扇の音が耐えられない |
| 視覚 | 蛍光灯のちらつきや強い光が不快 |
| 触覚 | 服のタグや素材が気になって集中できない |
| 嗅覚 | 香水や洗剤の匂いで気分が悪くなる |
| 味覚 | 特定の食感や味が受け付けない |
感覚過敏がもたらす日常の困りごと
感覚過敏はとても辛いものなのに、なかなか周りが理解してくれないという悪循環になることも多いです。
よくある困りごととしては以下の例が挙げられます。
- 学校や職場で集中できない
- 人混みや騒音でパニックになる
- 服や食事の選択肢が限られる
- 周囲に理解されず孤立感を感じる
これらの困りごとは、本人の努力だけでは解決が難しいこともあります。だからこそ、環境調整や工夫が重要です。
今日からできる!5つの生活改善法



環境などを改善することで、感覚過敏の方にも過ごしやすくなります。
1. 環境音をコントロールする
聴覚過敏の方には、以下のような対策が有効です。
- ノイズキャンセリングイヤホンの活用
- 静かな作業スペースの確保
- ホワイトノイズや自然音で環境音を中和
2. 光刺激を減らす
視覚過敏には、以下の工夫が役立ちます。
- 蛍光灯をLEDに変更する
- サングラスやブルーライトカット眼鏡の使用
- カーテンや間接照明で光量を調整



職場でサングラスは言いにくいかもしれませんが、企業は「何を配慮したらいいか分からない」ということが多いです。支援者を通じてもいいので、相談してみましょう。
3. 触覚のストレスを減らす
服の素材やタグなどが気になる場合は、以下の対策を試してみましょう。
- タグのない衣類を選ぶ
- 綿素材など肌触りの良い服を選ぶ
- 締め付けの少ない服を着る
4. 匂いの刺激を避ける
嗅覚過敏には、以下のような工夫が有効です。
- 無香料の洗剤や柔軟剤を使う
- 香水や芳香剤を避ける
- マスクで匂いを遮断する
5. 食事の工夫で味覚過敏に対応
食感や味に敏感な方には、以下のような工夫が役立ちます。
- 食べられるものをリスト化し、ローテーションする
- 調理法を変えて食感を調整する(例:蒸す→焼く)
- 無理に食べるのではなく、安心できる食環境を整える
支援者・家族ができること
理解と共感が第一歩
感覚過敏は「わがまま」ではなく、脳の特性によるものです。
まずは本人の感じ方を否定せず、共感する姿勢が大切です。
一緒に対策を考える
本人と一緒に「何がつらいのか」「どうすればラクになるか」を話し合い、環境調整を進めましょう。
支援者や家族の立場になると、相手のことを考えて「〇〇したらいいよ」「〇〇が絶対いいから」というように助言しがちになります。しかし、指示すると「自分のことは分かっていない」と逆に反発されるため、一緒に考え、本人の言葉から対策の言葉が出るよう「導き出すヒント」を出すことが大切。
記録をつけて傾向を把握する
困りごとや対策を記録することで、傾向が見えてきます。支援者・家族がサポートしやすくなります。
発達障害の方はメモを取るのが苦手なことが多いですが、工夫することで真剣に取り組んだりします。私も支援するうえでよくツールを活用しているのですが、以下の記事にアイデアを紹介しています。
まとめ:感覚過敏と向き合うために
感覚過敏は、発達障害のある方にとって日常生活に大きな影響を与える課題です。しかし、環境調整や工夫によって、少しずつ快適な生活を築くことは可能です。
この記事で紹介した5つの改善法は、すぐに実践できるものばかりです。ご本人だけでなく、支援者や家族の方も一緒に取り組むことで、安心できる生活環境が整っていくでしょう。
「できることから、少しずつ」実践することをおすすめします。それが感覚過敏と向き合う第一歩です。