私たちは日々、多くの思考に振り回されています。特に無意識に浮かぶ「自動思考」は、感情や行動に大きな影響を与えます。本記事では、自動思考の正体とそれに伴う「認知の歪み」を見抜き、より客観的に自分の思考を捉える方法を段階的に紹介します。
自動思考とは何か?
 支援員
支援員自動思考や認知の歪みは、就労移行などの支援者も実際の現場で精神障害や発達障害の方に説明することも多いです。
1. 自動思考の定義
自動思考とは、意識しないうちに瞬間的に浮かぶ思考パターンです。過去の経験や信念に基づき、反射的に頭に現れます。たとえば、プレゼン前に「また失敗するかも」と考える瞬間がこれに当たります。
2. 背後にあるメンタルブリーフィング
こうした思考は、無意識のうちに形成された「スクリプト(青写真)」によって支えられています。幼少期の経験や繰り返しの学習が積み重なり、特定の状況で自動的に思考が立ち上がる仕組みです。
認知の歪みとは?
1. 認知の歪みの概念
認知行動療法(CBT)で扱われる「認知の歪み」は、物事を歪んだフィルターで捉える思考クセを指します。自動思考と密接に結びつき、感情や行動を不必要にネガティブにします。
2. 主な認知の歪みの種類
| 歪みの種類 | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| 全か無か思考 | 白黒でしか考えない | 「完璧にできなければ無意味だ」 |
| 過度の一般化 | 一度の失敗をすべてに適用 | 「この企画がだめなら全て無駄だ」 |
| 心のフィルター | ネガティブ情報だけに注目 | 「ほめられても気づかない」 |
| 先読みの誤り | 未来を決めつける | 「絶対に評価されない」 |
実際に私が支援している事業所でも上記の例は多く存在し、思考と事実が異なるため、生活するうえでの生きづらさを持っています。
また、支援者視点の記事にはなりますが、認知のゆがみについては以下の記事でも詳しく解説しています。
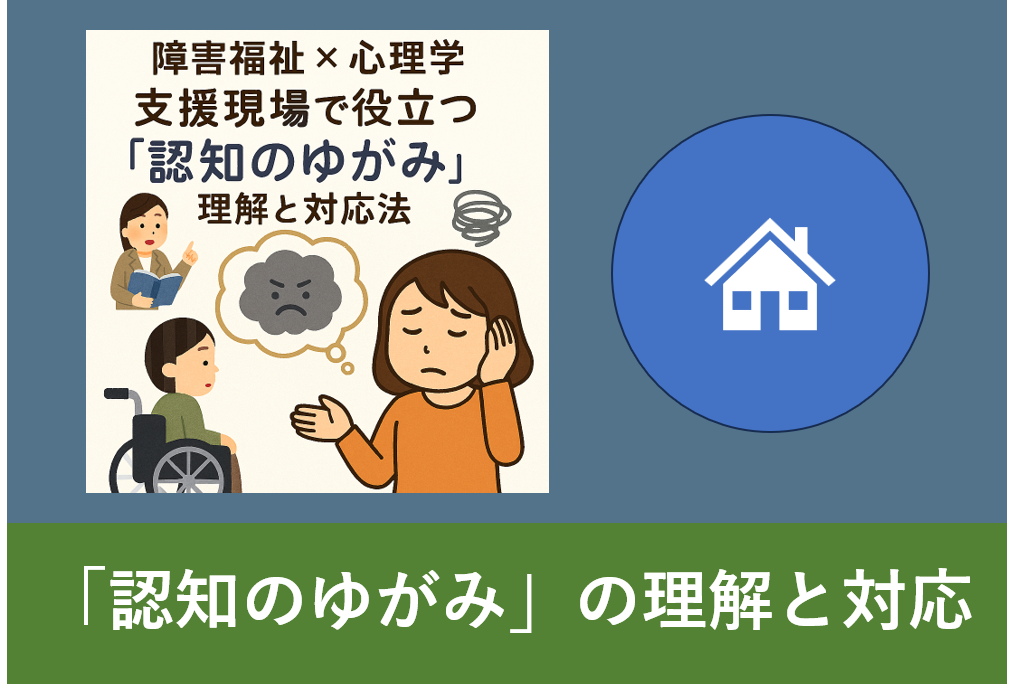
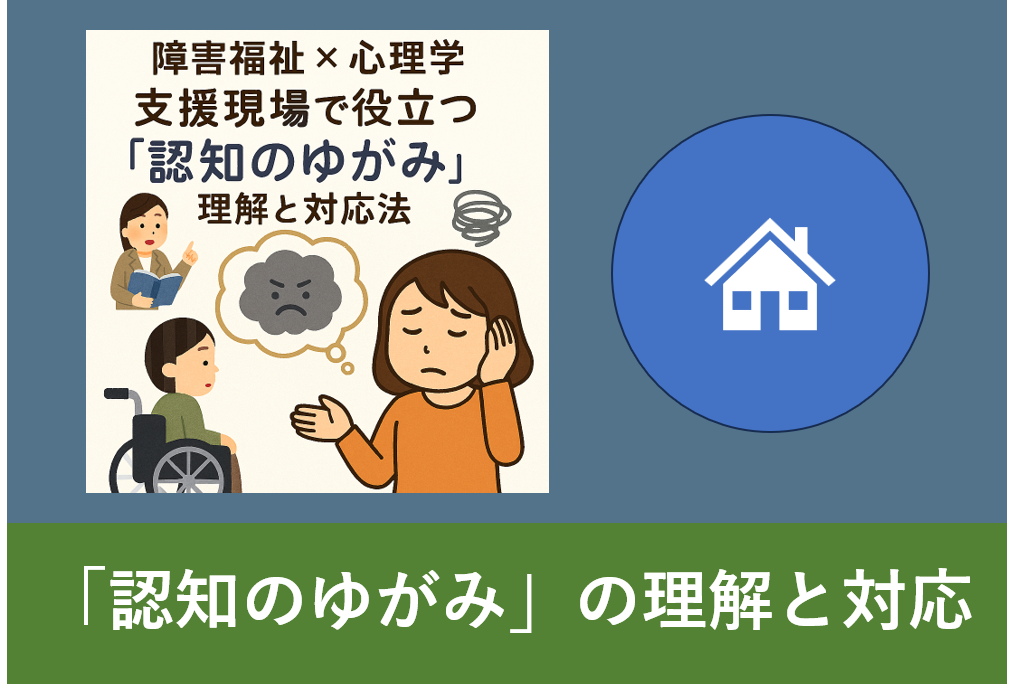
自動思考・認知の歪みに気づく方法
ご自身でできる認知の歪みへの対策を紹介します。
流れ
後から分析したり視覚化するためにもアウトプットする
呼吸を意識に向ける
それは本当に事実なのか
もう少し具体的に説明すると以下のようになります。
ステップ1:思考記録をつける
- 出来事と感情を書き出す
- 浮かんだ自動思考をそのまま記録
- 後から見返してパターンを分析
ステップ2:マインドフルネス的観察
呼吸に意識を向け、頭に浮かぶ思考を客観的に「雲のように通り過ぎるもの」として眺める訓練です。評価せず、ただ気づくことを目的とします。
ステップ3:質問で裏を探る
- 「それは事実か?」 本当に確認できるか?
- 「別の見方は?」 策はないか?
- 「最悪の結末は?」 どれだけ現実的か?
自動思考を書き換える実践テクニック



自動思考や認知の歪みを直すには時間が必要です。しかし、繰り返し実践することで改善に向かいます。
1. 事実検証と証拠集め
思考の裏付けとなる事実をリストアップし、強い確信を支える根拠を検証します。証拠が乏しければ、思考は仮説であると理解しましょう。
OK例:先輩が3日連続で欠席している。
NG例:先輩が自分を避けて会わないようにしている気がする
2. 代替思考の構築
ネガティブな自動思考に対し、「客観的でバランスの取れた視点」を意識して言い換えます。たとえば「失敗するかも」→「挑戦する価値はある。準備を整えよう」など。



私が支援するときは簡単なゲームとして「ポジティブ変換」というゲームをして、みんなで思考の気づきや言葉の言い換えを体験することも行いました。
「仕事が遅い」→「正確性が高い」というように、同じ部分でも見方を変えることで長所に変換できる。多くの物事は短所を長所に変換することができる
日常で習慣化するポイント
自動思考や認知の歪みを改善するには、一日や二日ではなく習慣化することがコツです。
- 毎日5分の思考観察タイムを確保
- 気づいた歪みをメモアプリに記録し続ける
- 週に一度、記録を振り返りパターン分析
- 信頼できるパートナーと振り返り会を開催
もし精神障害や発達障害などある方は、就労移行支援を利用して支援員と一緒に実施するのもおすすめです。


まとめ
自動思考と認知の歪みに気づくことで、感情の落ち込みや不安に振り回されにくくなります。「気づく力」を磨く習慣を日常に取り入れ、より柔軟で前向きな思考パターンを手に入れましょう。
私は支援員として福祉の仕事に就いたとき、先輩職員がご利用者へ「自動思考」や「認知の歪み」、そして「思考と事実の違い」を紙に書き出しながら説明していました。
私も同じ説明を実際に担当利用者に行いましたが、新しい気づきや自身の課題に自然と結びつきます。
今後よりよく働くためにも、是非活用していきましょう。
