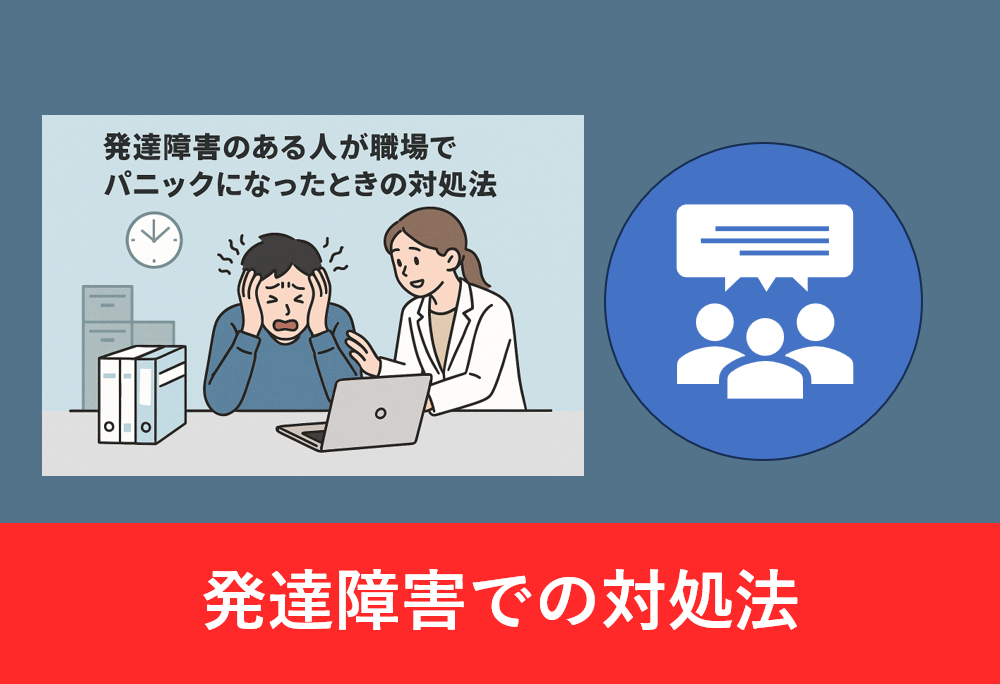職場で発達障害(ADHDやASDなど)のある人が突然パニックに陥ったとき、周囲の対応がその人の安心感や職場定着に大きく影響します。
この記事では、支援者や同僚が知っておくべき基本的な対処法から、事前の予防策、そして職場全体でできる環境づくりまでを詳しく解説します。
目次
発達障害のある人が職場でパニックになる理由
よくあるきっかけ
- 急な予定変更や指示の曖昧さ
- 騒音や人混みなどの感覚過敏
- 業務量の過多やプレッシャー
- 人間関係の摩擦や誤解
パニック時の主な症状
| 症状 | 具体例 |
|---|---|
| 過呼吸・動悸 | 息が荒くなり、胸が苦しいと訴える |
| 混乱・涙 | 話ができなくなり、泣き出すこともある |
| 過敏反応 | 音や光に過剰に反応し、耳をふさぐ |
| フリーズ・逃避 | その場から動けなくなる、席を離れる |
パニック時の具体的な対処法
 支援員
支援員職場でパニックになった後、落ち着いて対処を取ることで相手を守ることに繋がります。
1. 落ち着いた声かけと距離感
まずは本人の安全を確保し、落ち着いた声で「大丈夫」「まずは深呼吸して」と伝えましょう。無理に話しかけたり、触れたりするのは逆効果になることがあります。
2. 静かな場所へ誘導する
可能であれば、会議室や休憩室など静かな場所へ移動を促します。本人が動けない場合は、周囲の環境を整えることが優先です。
3. 呼吸を整えるサポート
過呼吸が見られる場合は、深呼吸を促す声かけや、紙袋を使った呼吸法なども有効です。ただし、医療的な対応が必要な場合はすぐに専門機関へ連絡しましょう。
4. 一人にしない・見守る
パニック時に一人にされると不安が増すことがあります。そばにいて見守るだけでも安心感につながります。
事前にできる予防策
本人との共有・合意形成
- 「パニックになりそうなときはどうしてほしいか」を事前に確認
- 支援者・上司・同僚との情報共有
- 緊急時の対応マニュアルを作成
環境調整の工夫
| 調整項目 | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 音・光の刺激 | イヤーマフやサングラスの使用、静かな席配置 |
| 業務量 | タスクの分割、優先順位の明確化 |
| コミュニケーション | 明確な指示、視覚的なサポート(メモ・図解) |
職場全体でできる支援体制の構築
1. 支援者の役割を明確にする
支援担当者やメンターを決めておくことで、本人が安心して相談できる環境が整います。
2. 定期的な振り返りと面談
業務の振り返りや感情面の確認を定期的に行うことで、パニックの予兆を早期に察知できます。
3. 社内研修の実施
発達障害に関する理解を深めるための社内研修や勉強会を定期的に開催することも有効です。
まとめ:安心できる職場づくりが最良の対処法
発達障害のある人が職場でパニックになることは、決して珍しいことではありません。
大切なのは、周囲が慌てず、理解と配慮をもって対応すること。そして、事前の準備や環境づくりが、本人の安心感と職場定着につながります。
支援者として、また同僚として、できることから一歩ずつ始めてみましょう。