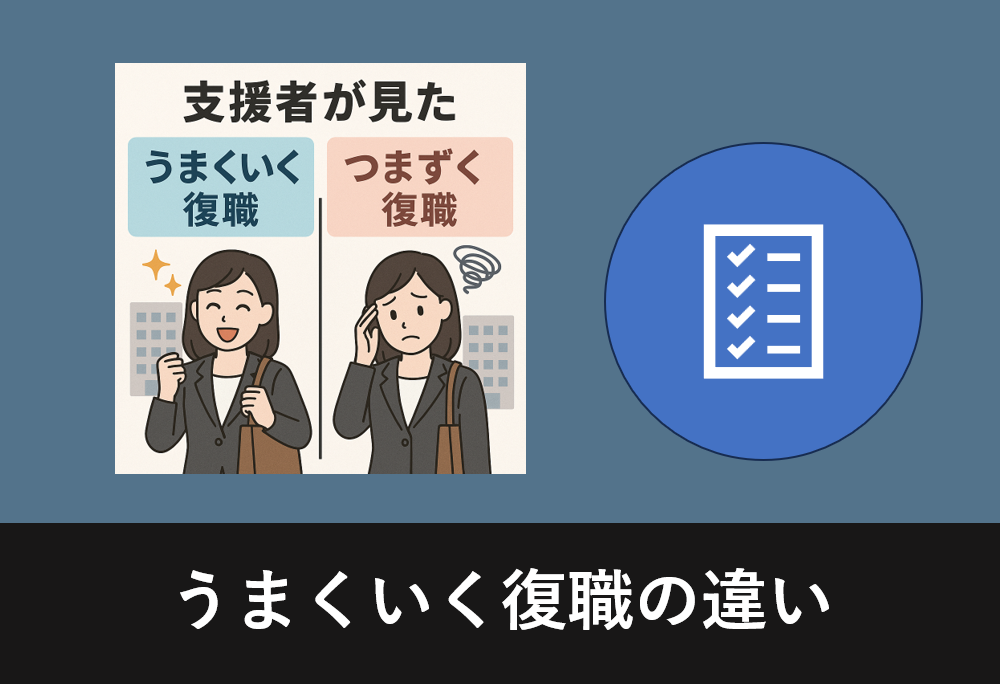はじめに:復職は“再スタート”ではなく“再構築”
復職は単なる職場復帰ではありません。心身の回復だけでなく、職場との関係性の再構築、業務への再適応、そして本人の自己理解と納得が求められる、非常に繊細で複雑なプロセスです。
支援者として現場で数多くの復職支援に関わってきた中で、うまくいくケースとつまずくケースには明確な違いがあることに気づきました。
本記事では、その違いを構造的に整理し、復職を成功に導くためのヒントを共有します。
うまくいく復職の特徴
① 本人の納得感と準備度
以下のような要素が揃っていると、復職はスムーズに進みやすくなります。
- 復職の目的や意義を本人が言語化できている
- 復職前から体調や生活リズムが安定している
- 休職になった要因と向き合っている
- 段階的な復職スケジュールが設計されている
② 職場の受け入れ体制
職場側の理解と柔軟性も重要です。以下のような対応があると、復職者の安心感が高まります。
- 上司や同僚が復職の背景を把握している
- 業務量や業務内容の調整がある
- 定期的な面談やフォローアップがある
③ 支援者との連携
支援者が単なる“付き添い”ではなく、復職の“伴走者”として機能しているケースでは、以下のような支援が行われています。
- 本人の不安や葛藤を言語化するサポート
- 職場との橋渡し役としての調整
- 復職後のモニタリングと早期介入
つまずく復職の特徴
 支援員
支援員私が支援してきた中でも、復職がうまくいかない特徴や、支援機関を使う前に失敗してきた体験談として聞いた共通点をお伝えします。
① 焦りや義務感による復職
「もう休めない」「周囲に迷惑をかけたくない」といった焦りや義務感から復職を急ぐと、以下のようなリスクがあります。
- 体調が不安定なまま復職してしまう
- 復職後すぐに業務負荷が高くなる(残業してしまう)
- 再休職につながる可能性が高まる
② 職場との認識のズレ
職場側が「もう元通り働ける」と誤解している場合、復職者との間に摩擦が生じます。
- 業務調整がされない
- 配慮が一時的で継続しない
- 復職者が孤立感を抱く
③ 支援の空白期間
復職直前や復職後に支援が途切れると、本人が不安定になりやすくなります。
- 復職直後の不安を誰にも相談できない
- 体調悪化に気づかれず、再休職に至る
復職がうまくいく方の成功事例



復職するまでに5か月ほどなど、休職期間をしっかり取った方は成功する確率が高くなっています。
就労移行支援や自立訓練事業所、職業センターなどリワーク支援を行っている機関に相談します。
焦って急ぐのではなく、振り返りやストレスマネジメントなども含めて復職時期を相談します。
休職になった原因と振り返ります。「限界まで一人で抱え込む」「ストレス発散が苦手」「コミュニケーションに課題」などが挙げられます。
同じように休職にならないよう、ストレスマネジメントやセルフケアの方法を模索します。
支援員と共に企業に訪問し、面談にて進捗を報告します。復職日直前だけだと心理的負担が大きくなるため、数回面談することが理想です。
業務内容や配置部署、勤務時間など調整します。
1人ではなく周りのサポートをうまく使う
休職した後、再度休職する方の多くは「一人で何でも解決しようとする人」です。
仕事であれば自立して解決することはもちろん大切ですが、就労移行や自立訓練などリワーク支援をサポートしている機関も多くありますので、利用して復職の支援を受けることをおすすめします。
支援者の視点から見た違いのまとめ
以下の表は、うまくいく復職とつまずく復職の違いを支援者視点で整理したものです。
| 項目 | うまくいく復職 | つまずく復職 |
|---|---|---|
| 本人の状態 | 納得感があり、準備が整っている | 焦りや義務感が強く、準備不足 |
| 職場の対応 | 柔軟な業務調整と継続的な配慮 | 復職者への理解不足、配慮が一時的 |
| 支援体制 | 復職前後で継続的な支援がある | 復職直前・直後に支援が途切れる |
支援者ができること:復職成功のための伴走
① 本人の声を引き出す
「本当に復職したいのか」「何が不安なのか」を丁寧に聞き出すことで、本人の納得感を高めることができます。
② 職場との橋渡し
支援者が職場と本人の間に立ち、以下のような調整を行うことが重要です。
- 業務内容や勤務時間の調整
- 復職後のフォロー体制の提案
- 職場内の理解促進(研修や説明など)
③ 再休職を防ぐモニタリング
復職後も定期的に面談やチェックインを行い、早期に兆候を察知することが再休職の予防につながります。
おわりに:復職は“ゴール”ではなく“通過点”
復職は決してゴールではありません。むしろ、そこから始まる“再構築”のプロセスこそが本質です。支援者として、本人の声に耳を傾け、職場との橋渡しを行い、継続的な伴走をすることで、復職の成功率は大きく高まります。
この記事が、復職支援に関わるすべての方にとって、実践的なヒントとなることを願っています。