仕事中に突然大きな音が気になって集中できなくなったり、電車の揺れで疲れやすかったりなど、大人の発達障害では、五感を通じた情報処理のズレが日常生活や職場でのストレスを増幅させることがあります。
本記事では、感覚統合の基本的な仕組みを押さえつつ、発達障害との関連性を解説。具体的なサインやセルフケア、専門的支援のポイントまで、働く大人に役立つ情報を網羅的にお届けします。
感覚統合とは?
まずは感覚統合の意味や基礎知識を紹介します。
感覚統合の概要
感覚統合とは、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感から入ってくる情報を中枢神経で整理・統合し、適切に行動や認知へつなげるプロセスを指します。外界の刺激を「感覚入力」、脳内での処理を「感覚統合」、結果として生じる行動を「感覚運動反応」と呼ぶこともあります。
五感と脳の関係
感覚情報は五感それぞれの神経を通じて大脳皮質に伝わり、脳内で「どの程度の強さか」「どんな質なのか」を判別します。統合された情報は前頭葉や大脳辺縁系に送られ、行動選択や情動反応が生まれます。
 支援員
支援員聴覚や味覚など、それぞれ役割が分かれています。
| 感覚 | 主な役割 | 入出力の例 |
|---|---|---|
| 視覚 | 情報の認識・環境把握 | 光/色・形を把握 |
| 聴覚 | コミュニケーション・危険察知 | 音声/雑音の区別 |
| 触覚 | 皮膚での刺激認識 | 温度や圧の感じ取り |
| 味覚 | 栄養判断・嫌悪反応 | 甘味・苦味の区別 |
| 嗅覚 | 危険察知・情動との結び付け | においの識別 |
発達障害と感覚統合の関連性
発達障害(自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害など)の特性として、感覚情報の処理が過敏または鈍くなることがあります。これが感覚過敏や感覚鈍麻を引き起こし、日常生活の困難度を高める要因となります。
感覚過敏のサイン
- 蛍光灯のチカチカが頭痛につながる
- 服のタグや素材感が耐えられない
- 雑踏や騒音環境でパニックになりやすい
- 食べ物の食感やにおいに極端に反応
感覚鈍麻のサイン
- 温度変化に気づきにくい
- 痛みを感じにくくケガに気づかない
- 身体の位置感覚(プロプリオセプション)がつかめず動作が不安定
感覚過敏については以下の記事でも解説しています。
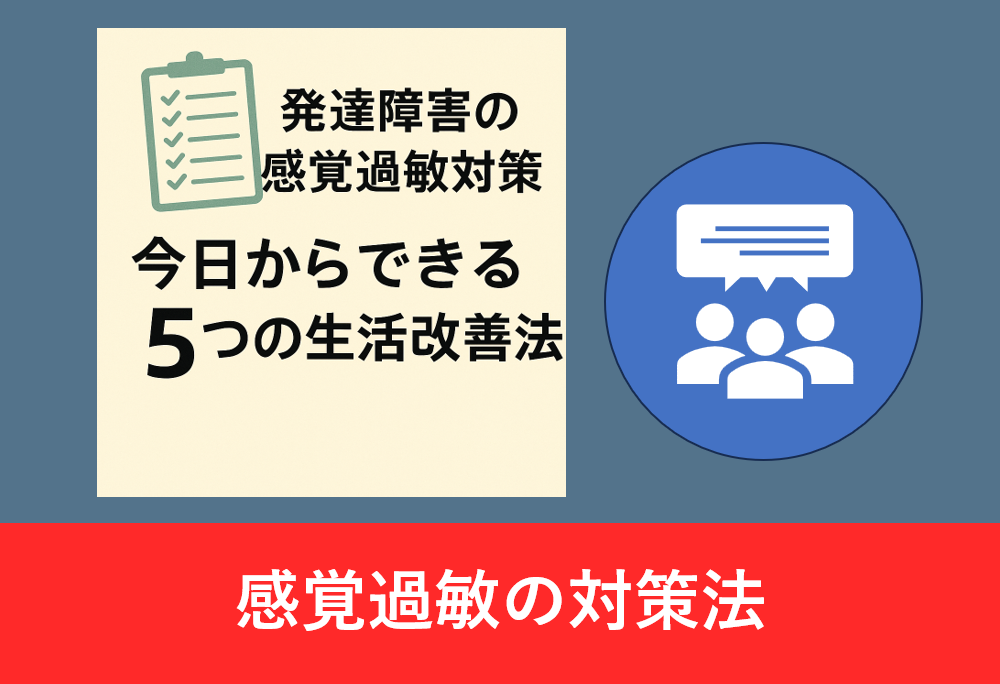
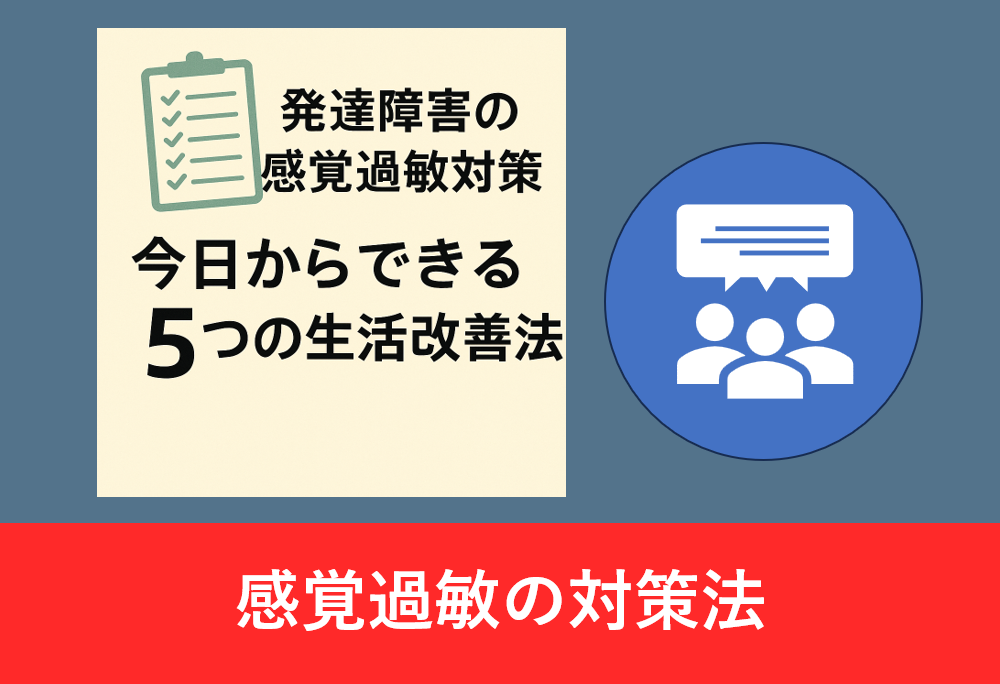
感覚統合がうまく機能しない場合の具体例
大人の職場や家庭で起こり得る課題を挙げると、以下のようなケースがあります。
- 会議中の雑音で集中力が切れ、メモが取れない
- 満員電車で周囲の圧迫感に耐えられず、体調を崩す
- Web会議のマイクオン/オフ音にイライラし、発言をためらう
- 仕事帰りの疲労感が異常に強く、休日も寝たきりになる



仕事をしていると「自分だけなんでこんなにしんどいんだろう」と責めてしまうことがありますが、それが実は感覚統合がうまく機能していない可能性もあります。
働く大人のための感覚統合サポート方法
実際に仕事で働く場合、セルフケアや環境調整、サポートを受けることでよりよく働くことに繋がります。
セルフケアと環境調整
- ノイズキャンセリングヘッドホンで不要な音をシャットアウト
- 視覚刺激の制御:デスク周りをシンプルに整理・淡色LED照明を活用
- 触覚刺激の活用:ウェイトブランケットやストレスボールで安心感を得る
- 休憩ルーチン:定期的に短時間のストレッチや深呼吸を挟む
専門家のサポート
感覚統合療法(OT)や作業療法士の指導のもと、五感への刺激量を調整するプログラムを試す方法があります。訓練を継続することで、日常的なストレス耐性の向上や自己調整能力の獲得が期待できます。
感覚統合サポート実践例
次は、感覚統合の実践例やポイントを紹介します。
以下の表を見てみましょう。
| 方法 | 目的 | 導入のポイント |
|---|---|---|
| ノイズキャンセリングヘッドホン | 聴覚刺激の軽減 | 職場での使用許可を事前に取得 |
| ウェイトブランケット | 触覚的な安心感の提供 | 重量やデザインを試し、肌触りを確認 |
| 光目覚まし時計 | 朝の覚醒リズム改善 | 自然光に近いLEDを選択 |
| マインドフルネス瞑想 | 自己調整力の強化 | 1日5分から継続する |
また、今の会社ではどうしてもストレスになったり配慮がうまくいかないという場合は、仕事を変えるという選択肢もあります。
まとめ
発達障害を抱える大人にとって、感覚統合のズレは“見えない負荷”となり、仕事や人間関係に影響を及ぼします。本記事では、感覚統合の基本メカニズムと発達障害との結びつき、具体的サイン、セルフケア・専門ケアの方法までを紹介しました。
自分に合ったサポート方法を見つけ、日常のストレスを軽減する一歩を踏み出しましょう。
