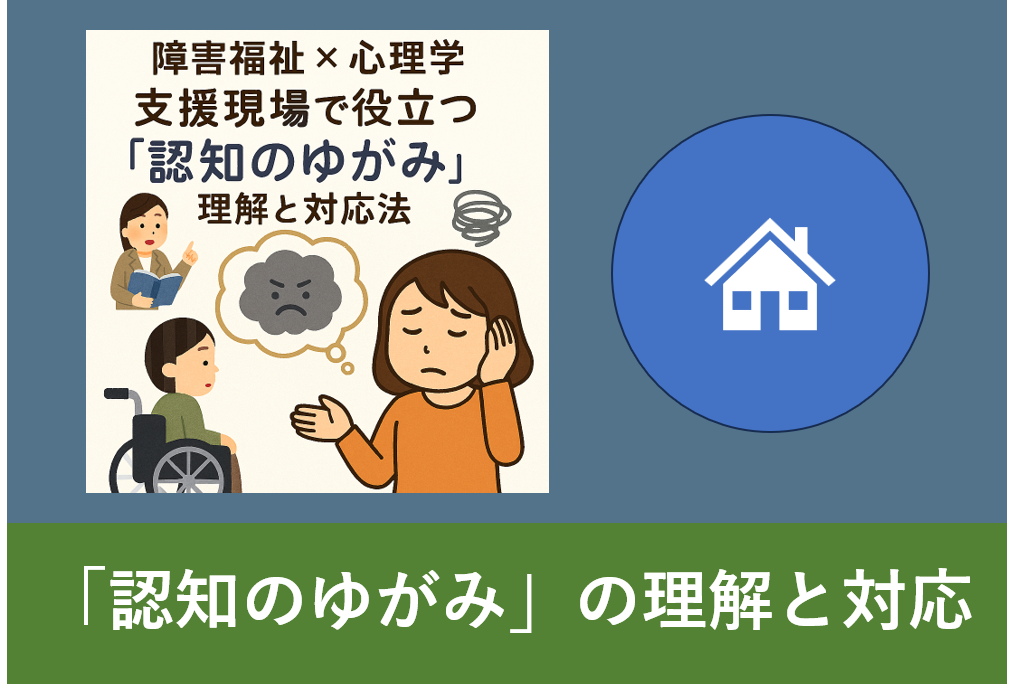障害福祉の支援現場では、利用者の言動や感情の背景に「認知のゆがみ」が潜んでいることがあります。認知のゆがみとは、物事の捉え方や思考パターンが偏ってしまう心理的傾向のこと。
これを理解し、適切に対応することで、支援の質が大きく向上します。
本記事では、認知のゆがみの代表的な種類とその支援現場での具体的な対応法を、心理学の視点から解説します。
私は普段発達障害や精神障害の方の支援を行ていますが、支援者が「なぜこのような反応をするのか?」と悩んだときの参考になれば幸いです。
認知のゆがみとは何か?
認知のゆがみの定義
認知のゆがみ(Cognitive Distortion)とは、現実の出来事を歪んだ視点で捉えてしまう思考のクセのことです。これは誰にでも起こり得るもので、特にストレスや不安が強いときに顕著になります。
代表的な認知のゆがみ一覧
認知の歪みの中でも代表的なものや支援現場での例を紹介します。
| 種類 | 説明 | 支援現場での例 |
|---|---|---|
| 全か無か思考 | 物事を白か黒かで判断し、中間を認めない | 「できなかった=自分はダメだ」と思い込む |
| 過度の一般化 | 一度の失敗をすべてに当てはめる | 「一度断られた=誰にも受け入れられない」 |
| 心のフィルター | ネガティブな情報だけを選んで見る | 褒められても「でも失敗した部分がある」と否定する |
| マイナス思考 | ポジティブな出来事を否定的に解釈する | 「褒められたのはお世辞だ」と受け取る |
| 感情的決めつけ | 感情を根拠に事実を判断する | 「不安だから、きっと失敗する」と思い込む |
支援現場での「認知のゆがみ」への対応
 支援員
支援員支援を行っていると、「認知のゆがみ」と感じる例は毎日のようにみます。その中でも、対応として注意することや有効だったことをお伝えします。
1. 否定せず、まずは受け止める
認知のゆがみを指摘する前に、まずはその人の感じている不安や怒りを受け止めることが重要です。
否定されると防衛的になり、支援が進みにくくなります。
- 「そう感じるのは自然なことです」
- 「その考え方には理由があるんですね」
2. ゆがみの種類を見極める
言動の背景にある思考パターンを観察し、どの認知のゆがみが働いているかを見極めましょう。上記の表を参考に、発言の傾向を把握することがポイントです。
3. リフレーミングで視点を変える
リフレーミングとは、物事の見方を変えることで新しい意味づけをする技法です。認知のゆがみをやわらげるために有効です。
- 「失敗した=成長のチャンスだったかもしれませんね」
- 「断られた=他の選択肢を探すきっかけになった」
- 「また休んでしまった=体が休みを必要としていただけ」
- 「友達に急に断られた=空いた時間に余裕ができた」
4. 小さな成功体験を積ませる
認知のゆがみは自己肯定感の低さと関係していることが多いため、小さな成功体験を積み重ねることで思考の柔軟性が育まれます。
小さな成功の例としては、自己効力感も当てはまります。
5. 支援者自身の認知のゆがみにも注意
支援者もまた、知らず知らずのうちに「こうあるべき」「この人はこういうタイプだ」といった思い込みにとらわれることがあります。定期的な振り返りやスーパービジョンを通じて、自身の認知のゆがみを見直すことも大切です。
事例紹介:認知のゆがみが支援に影響したケース
ケース1:就労支援での「全か無か思考」
ある利用者は、面接で不採用になったことを「自分は社会に必要とされていない」と極端に捉えていました。支援者は「一社の結果がすべてではない」と伝えつつ、過去の成功体験を一緒に振り返ることで、少しずつ視点を広げることができました。
ケース2:生活支援での「心のフィルター」
日常生活で褒められても「でも昨日は失敗した」とネガティブな面ばかりに注目する利用者に対し、支援者は「昨日の失敗も、今日の成功も、どちらもあなたの一部です」と伝え、両面を受け入れる姿勢を促しました。
支援者が身につけたい視点とスキル



認知のゆがみは様々なパターンがありますが、支援者のスキルは必ず日々上がります。そして、是非身に付けておきたいスキルを紹介します。
心理学的視点を持つメリット
- 利用者の言動の背景を理解できる
- 感情的な反応に振り回されずに対応できる
- 支援の質が安定し、信頼関係が築きやすくなる
おすすめのスキル・知識
| スキル・知識 | 概要 |
|---|---|
| 認知行動療法(CBT) | 認知のゆがみを修正する心理療法。支援者にも応用可能 |
| リフレーミング技法 | 物事の見方を変えることで、感情や行動を柔軟にする |
| アサーション | 自分も相手も尊重するコミュニケーション技法 |
まとめ:認知のゆがみを理解することが支援の第一歩
認知のゆがみは、障害福祉の支援現場において非常に重要な視点です。利用者の言動に対して「なぜそうなるのか?」と疑問を持ったとき、心理学的な理解があると対応の幅が広がります。
支援者自身もまた、認知のゆがみにとらわれない柔軟な視点をもつことで、幅広い支援に繋がります。