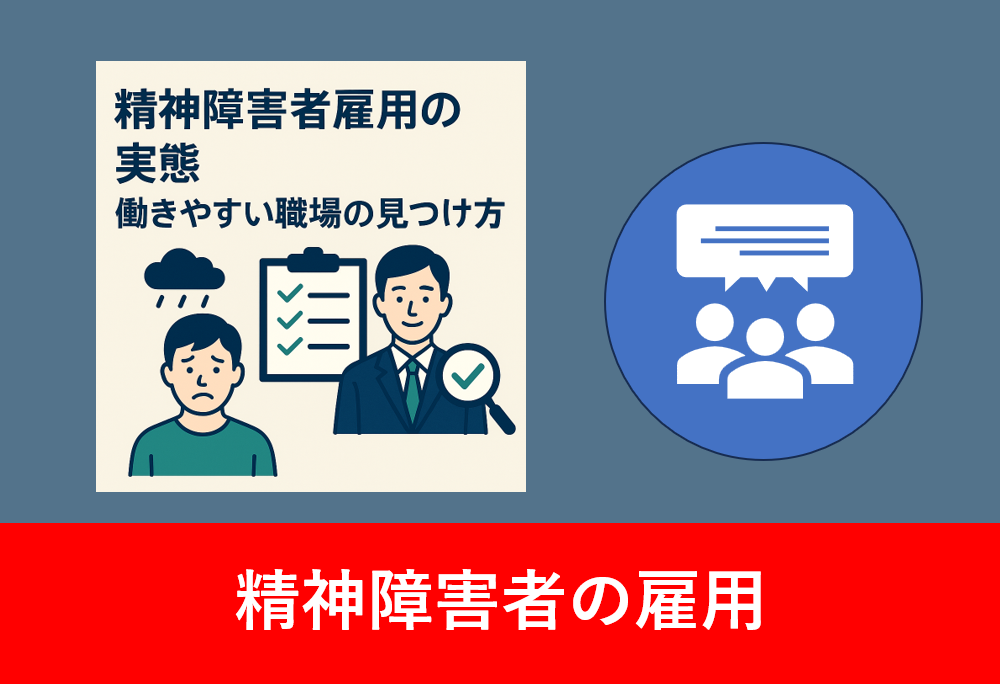近年、精神障害者の雇用は、障害者雇用促進法の改正や合理的配慮の義務化など、法制度の整備とともに着実に進展しています。
企業の意識も徐々に高まり、精神障害を抱える方々が社会の一員として働く機会は増えつつあります。しかし、実際の職場環境に目を向けると、症状への理解不足や支援体制の不備、業務内容のミスマッチなど、現場レベルでは依然として多くの課題が残されています。
本記事では、精神障害者雇用の現状をデータや制度面から整理しつつ、実際に働く人々が直面する課題や職場での困りごとに焦点を当てます。
そのうえで、働きやすい職場を見つけるために押さえておきたいポイントや、面接時に確認すべき事項、支援機関の活用方法など、実践的なノウハウを具体的に紹介します。
精神障害者雇用の現状と課題
法制度の整備と雇用義務
2018年の障害者雇用促進法改正により、精神障害者も法定雇用率の対象となりました。企業は一定数以上の障害者を雇用する義務があり、精神障害者の雇用も増加傾向にあります。
■精神障害者を雇用する企業は増加傾向
- 法定雇用率:民間企業で2.3%、国・地方公共団体で2.6%
- 精神障害者の雇用者数は年々増加(厚労省調査より)
- 就労支援機関との連携が進む一方、職場定着率には課題
職場での課題
雇用数が増えている一方で、職場での理解不足や支援体制の不備により、離職率が高い傾向があります。
- 症状への理解不足による誤解や偏見
- 業務量やコミュニケーションへの配慮が不十分
- 支援担当者の不在、または専門性の不足
 支援員
支援員障害者枠の雇い主も、精神障害者の雇用が初めてという方も少なくありません。何を配慮し、どう対応したらいいか手探りの担当もいます。
働きやすい職場の特徴
合理的配慮がある職場
精神障害者が安心して働ける職場には、合理的配慮について担当が理解されています。
| 配慮項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 勤務時間の調整 | 週3日勤務、午後からの勤務など | 疲労軽減 |
| 作業環境の配慮 | 静かな場所、パーテーション | 不安軽減 |
| 業務内容の調整 | ルーティン業務 | 集中力向上 |
| 定期面談の実施 | 月に1回面談 | 早期の課題発見 |
| 教育担当の固定 | 業務指示する社員の統一 | 優先順位が明確 |



私が担当した企業では、週4日勤務から段階的に勤務日数を増やし、3年後には週5日フルタイムに増えて安定して勤務された方もいます。
支援体制が整っている
職場内に支援担当者(ジョブコーチや産業保健スタッフ)がいることで、日常の困りごとや不安を相談しやすくなります。また、就労移行や自立訓練事業所を通じて就職された方は支援員がサポートしていることも多いです。
ジョブコーチとは?
ジョブコーチには訪問型や企業在籍型などさまざま。精神障害者などの潜在能力を活かすため、業務内容や業務時間を一緒に考えたり、企業の上司に助言なども行う。職業センターから派遣することもあれば、企業の従業員がジョブコーチと兼任されている場合もある。
職場文化と人間関係
障害に対する偏見が少なく、オープンなコミュニケーションが取れる職場は、精神障害者にとって働きやすい環境です。
- 上司や同僚の理解がある
- 障害を開示しても不利益がない
- チームで支え合う文化がある
私が支援員として同行した企業の中には、「配慮が必要なことはもちろん配慮する。逆にその人ができることは他の人と同じように作業してもらい、能力を高めてほしい」という考えをもった企業も複数ありました。
働きやすい職場の見つけ方
就労支援機関の活用
ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などを活用することで、職場選びのサポートが受けられます。
- 職場実習やトライアル雇用の紹介
- 入社日や勤務日数、時間などの調整
- 職場定着支援やジョブコーチ派遣
- 履歴書・面接対策の支援
- 面接同行
企業の障害者雇用実績を調べる
企業の障害者雇用に関する情報は、企業HPや厚労省の「障害者雇用状況報告」などで確認できます。
面接時に確認すべきポイント
面接では、以下の点を確認することで職場の配慮体制を見極めることができます。
| チェック項目 | 質問例 | 理想的な回答 |
|---|---|---|
| 障害者雇用の実績 | 「精神障害の方は何名働いていますか? | 理想的な現在5名在籍し、定着率も高いです |
| 支援体制の有無 | 支援担当者やジョブコーチはいますか? | 教育担当とジョブコーチがいます |
| 業務内容の柔軟性 | 業務内容は相談可ですか? | 相談可能です |
| 配慮が可能か | 過去にどんな配慮をされた方がいますか? | 勤務時間や部署、業務内容など |
職場定着のためにできること



実際に働こうと思うと不安が強いです



企業も長く安定して働いてほしいと思っていますので、コツを抑える必要があります。
自己理解と情報開示
自分の症状や得意・不得意を理解し、必要な配慮を伝えることが職場定着の第一歩です。
例えば精神障害者の方を支援しているときによく悩まれているのが「休憩時間に1人になりたい」など。事前に人事担当に伝えておくことで、必要以上にコミュニケーションを取って疲れるリスクを減らせます。
支援者との連携
支援機関や医療機関との連携を保ち、職場での困りごとを早期に共有することで、離職リスクを減らせます。
就労移行などの支援機関によっては病院への通院同行も行えますので、企業に伝える配慮事項など打ち合わせができます。
無理をしすぎない働き方
精神障害は波があるため、無理をせず、体調に応じた働き方を選ぶことが重要です。
- 週3日や4日の勤務からスタート
- 在宅勤務や短時間勤務の活用
- 定期的な休息とセルフケアの実践
まとめ
精神障害者雇用は制度面では進展していますが、職場環境や支援体制にはまだ改善の余地があります。
働きやすい職場を見つけるには、支援機関の活用や企業情報の収集、面接での確認が重要です。
また、職場定着には自己理解と支援者との連携が欠かせません。
精神障害を抱えながらも、自分らしく働ける職場は必ずあります。焦らず、着実に、自分に合った環境を見つけていきましょう。