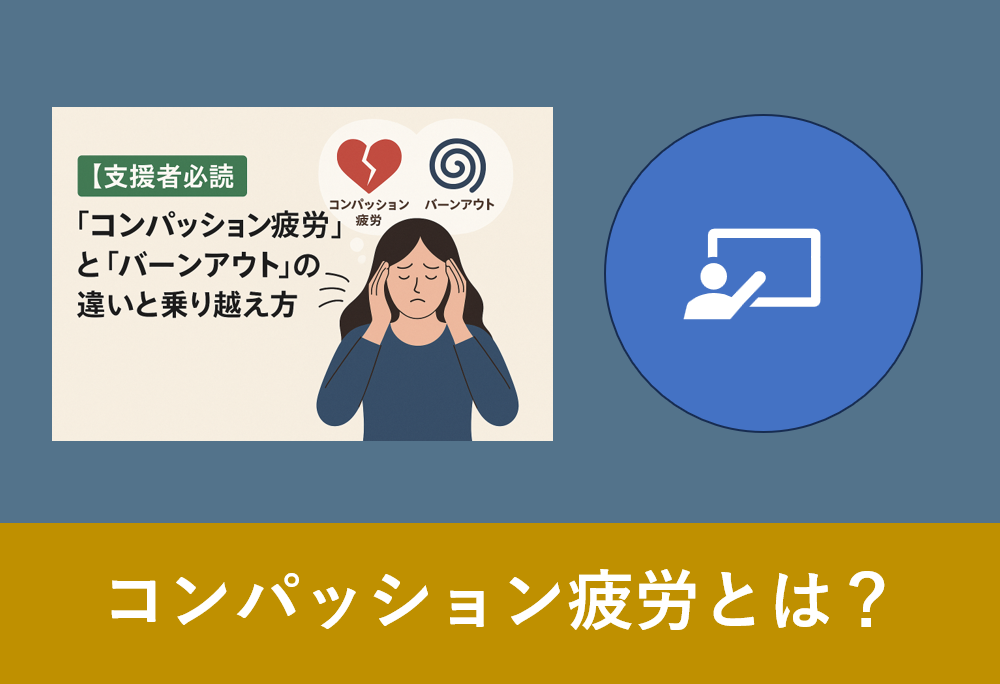福祉・医療・教育などの支援現場で働く方々は、日々他者の苦しみに寄り添いながら、心身に大きな負荷を抱えています。
そんな中で注目されているのが「コンパッション疲労」と「バーンアウト」という2つの心理的状態です。
本記事では、支援者が陥りやすいこの2つの状態の違いと、それぞれへの具体的な対策について解説します。
現場での実践に役立つセルフケアの視点も交えながら、支援者自身が健やかに働き続けるためのヒントをお伝えします。
コンパッション疲労とバーンアウトの違いとは?
それぞれの定義
| 名称 | 定義 | 主な原因 |
|---|---|---|
| コンパッション疲労 | 他者の苦しみに共感しすぎることで、心理的に疲弊する状態 | 共感疲労、感情移入、トラウマの二次受傷 |
| バーンアウト | 慢性的なストレスにより、情熱や意欲が枯渇する状態 | 業務過多、役割の曖昧さ、達成感の欠如 |
症状の違い
 支援員
支援員この2つの名称はよく間違えられやすいのですが、原因が「他者への共感」か「仕事のストレス」など大きく違います。
- コンパッション疲労:感情的な疲れ、無力感、他者への共感の低下
- バーンアウト:仕事への興味喪失、イライラ、身体的疲労、離職願望
混同されやすい理由
両者とも「疲弊」や「やる気の低下」を伴うため、現場ではしばしば混同されます。しかし、コンパッション疲労は“他者の苦しみ”に起因する共感疲労であり、バーンアウトは“業務環境”に起因する慢性ストレスという違いがあります。
そして、コンパッション疲労はバーンアウトの一種、もしくはそこに繋がる要因とも言われているため、混同されやすくなっています。
支援者が陥りやすい背景



障害福祉の中で支援者の方も直面するのですか?



私も支援員を長く行っていますが、福祉の方は「相手のために何ができるか」を常に考える傾向があり、共感したり寄り添う気持ちが高すぎる方にもよく起きます。
支援職特有の構造的要因
以下は支援者の現場での要因とした例です。
- 感情労働が中心である
- 成果が見えにくく、達成感を得づらい
- クライアントの苦しみに長期的に寄り添う必要がある
- 支援者自身のケアが後回しになりがち
現場でよくある声
私の同僚などでも退職していった方なども見てきましたが、以下のような悩みも聞きました。
- 支援しても状況が変わらない
- 自分の支援が意味あるのか分からない
- 感情が揺さぶられすぎて疲れる
精神障害や発達障害の方には辛い経験を持っている方も多いので、本気で支援しているほど感情が揺さぶられやすくなりますので注意が必要です。
以下の記事も参考になります。
乗り越えるためのセルフケア戦略
支援者も同じ人間のため、自身を守ることが大切です。
以下はセルフケアの方法を紹介します。
① 自己理解と感情の棚卸し
まずは自分の感情に気づき、言語化することが重要です。以下のような問いを定期的に振り返る習慣を持ちましょう。
- 最近、どんな場面で疲れを感じたか?
- 共感しすぎて苦しくなった瞬間は?
- 自分の限界を超えていないか?
② 境界線(バウンダリー)の意識
支援者は「相手の苦しみ=自分の責任」と感じやすい傾向があります。私も支援するうえで、必要以上に抱え込むことが多くありました。
そこで、以下のような意識が大切です。
- 「できること」と「できないこと」を明確にする
- 相手の感情を“受け止める”が“背負わない”
- 支援者としての役割と個人としての感情を分ける
③ 支援者同士の対話と共有
孤立感は疲労を加速させます。同じ立場の支援者同士で、感情や経験を共有する場を持つことが回復の鍵になります。
- 定期的なケースカンファレンス(ケース会議)
- ピアサポートグループ
- 医療や関係機関との連携
私も支援するうえで気を付けているのが、役割分担です。
例えば「自身が指導する役割」とすると「相談員がフォローする役」「主治医が医療の分野で的確に助言」など、事前に打ち合わせを行います。
自分だけが関わっていると障害を持つ方が自分に対して攻撃的になることも多いので、一人で抱え込まないのが大切です。
④ 専門家の力を借りる
心理的な疲労が深刻な場合は、臨床心理士やカウンセラーなど専門家の支援を受けることも選択肢です。セルフケアだけで抱え込まず、外部資源を活用しましょう。
支援者としての「レジリエンス」を育てる
日常に取り入れたい3つの習慣
| 習慣 | 具体例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| リフレクション | 日記や振り返りメモをつける | 感情の整理と自己理解の促進 |
| セルフコンパッション | 「自分も苦労している」と認める | 自己否定の軽減と回復力の向上 |
| マインドフルネス | 呼吸法や瞑想を取り入れる | ストレス軽減と集中力向上 |
リフレクションとは
リフレクション(reflection)は内省を意味する言葉。自身の考えや言動を深く省みること。ずっと仕事を続けていると視野も狭くなるため、仕事から一時的に離れて考えや行動を振り返ることをリフレクションとして使われる。新入社員や従業員などへの育成でも使われる。
まとめ:支援者自身のケアが、支援の質を高める
「コンパッション疲労」と「バーンアウト」は、支援者が真摯に向き合っている証でもあります。しかし、支援者自身が疲弊してしまっては、継続的な支援は困難になります。
まずは自分の状態に気づき、ケアすること。それは決して甘えではなく、支援の質を高めるための戦略的な選択です。