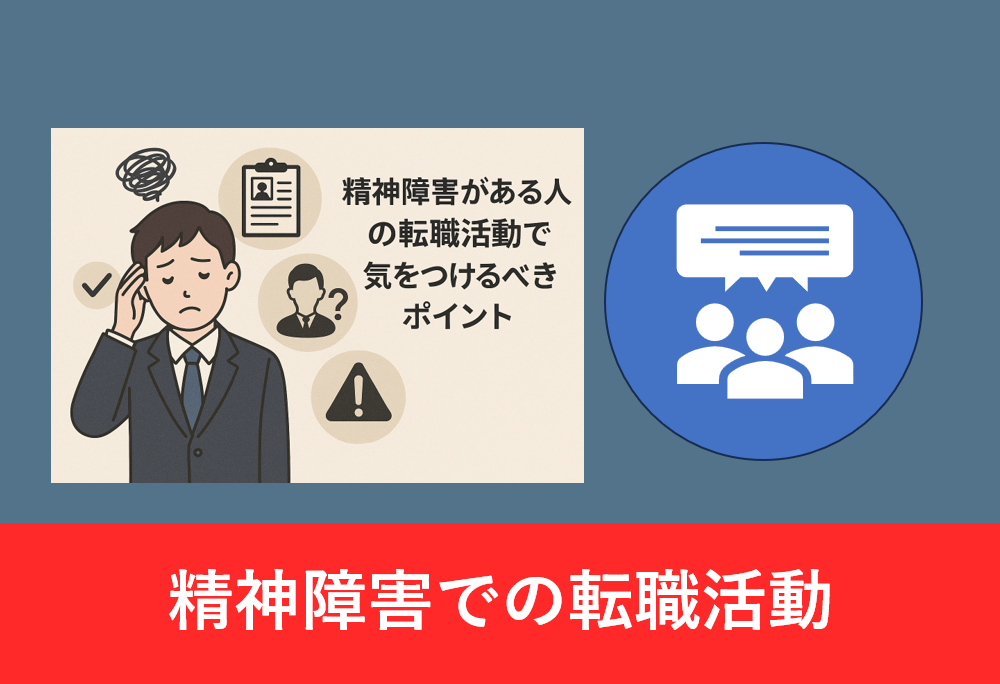精神障害を抱える方にとって、転職活動は大きな挑戦です。体調の波や職場環境への不安、面接時の自己開示の悩みなど、一般的な転職活動とは異なる配慮が必要になります。
しかし、適切な準備と情報をもとにすれば、自分に合った職場を見つけることは十分可能です。
この記事では、精神障害がある方が転職活動を進める際に気をつけるべきポイントを、実践的な視点から解説します。
転職活動前に整理しておきたいこと
自分の障害特性と働き方の希望を明確にする
転職活動を始める前に、自分の障害特性と働き方の希望を整理しておくことが重要です。以下のような項目を紙やスプレッドシートに書き出してみましょう。
- 得意な業務・苦手な業務
- 体調の波や通院頻度
- 希望する勤務時間・勤務形態(フルタイム/パート/在宅など)
- 職場に求める配慮(静かな環境、柔軟な休憩など)
支援機関や制度の活用
精神障害がある方の転職活動では、以下のような支援制度や機関の活用が有効です。
| 支援制度・機関 | 内容 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 職業訓練や対人訓練、面接練習などをサポート |
| ハローワーク(障害者窓口) | 障害者向け求人の紹介や職業相談 |
| 障害者職業センター | 職業評価やジョブコーチ |
| 障害者手帳の活用 | 合理的配慮の申請や障害者雇用枠の利用が可能 |
合理的配慮については以下の記事も参考になります。
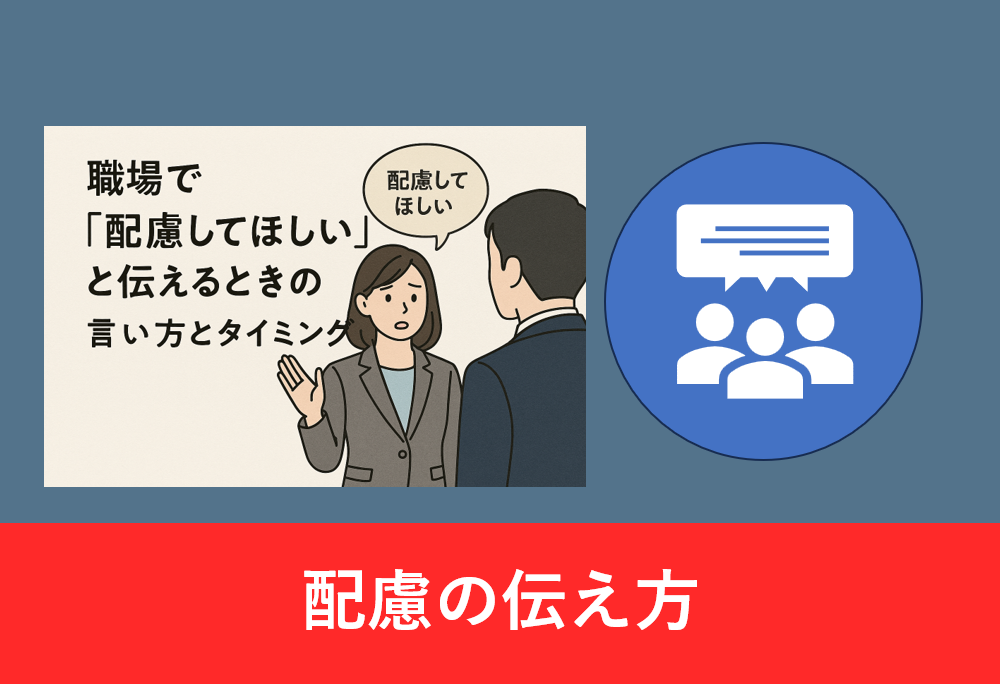
求人選びのポイント
 支援員
支援員自身に合った職場を選ぶためにも、求人の選び方はとても重要です。
障害者雇用枠の活用
精神障害がある方は、障害者雇用枠での応募を検討することで、職場での配慮を受けやすくなります。法定雇用率を満たすため、企業によっては、障害者雇用枠での採用に積極的なところもあります。
障害者の雇用の促進として、法律で「障害者雇用率制度」を定めており、事業主に対して常時雇用している労働者に障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけられている。令和5年度以降の民間企業は2.3%以上、令和6年度2.5%以上、令和8年7月から2.7%というように段階的に増やされている。
企業の理解度を見極める
求人票や企業のホームページ、口コミサイトなどを活用して、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 障害者雇用の実績があるか
- 合理的配慮の事例が紹介されているか
- メンタルヘルスに関する制度(産業医、相談窓口など)があるか
応募・面接時の注意点
障害の開示と配慮の伝え方
障害の開示は任意ですが、職場での配慮を求める場合は、ある程度の情報提供が必要です。以下のような伝え方が効果的です。
- 診断名と共に、「どんな困りごとがあるか」を中心に伝える
- 過去の職場での工夫や成功体験を交えて話す
- 希望する配慮を具体的に伝える(例:週1回の通院配慮、静かな席など)
面接でよく聞かれる質問と回答例
| 質問 | 回答例 |
|---|---|
| これまでの職歴について教えてください | 「○○業界で○年間勤務し、主に○○業務を担当していました。業務の中で工夫した点は…」 |
| 障害について教えていただけますか? | 「○○という診断を受けていますが、現在は○○の工夫により安定しています。業務上は○○に配慮いただけると助かります」 |
| どのような働き方を希望されますか? | 「週○日、○時間の勤務を希望しています。体調に波があるため、柔軟な休憩時間をいただけると助かります」 |



私が精神障害の方の面接同行に行った際は「気持ちが落ち込んだ時の自分で行う対処法」「勤怠は安定ていますか?」「いつ発症しましたか?」などの質問も多くありました。
入社後に気をつけたいこと
職場とのコミュニケーション
入社後も、体調や業務の進捗について定期的に上司や支援担当者と話す機会を持つことが重要です。無理をせず、早めに相談する習慣をつけましょう。
セルフケアと支援の継続
転職後も、通院や服薬、生活リズムの維持など、セルフケアを継続することが安定就労につながります。必要に応じて支援機関との連携も続けましょう。
まとめ
精神障害がある方の転職活動には、特有の課題と工夫が必要です。しかし、事前準備と支援制度の活用、そして自分に合った働き方の模索によって、安心して働ける職場を見つけることは可能です。
この記事が、転職活動に踏み出す一歩の支えとなれば幸いです。