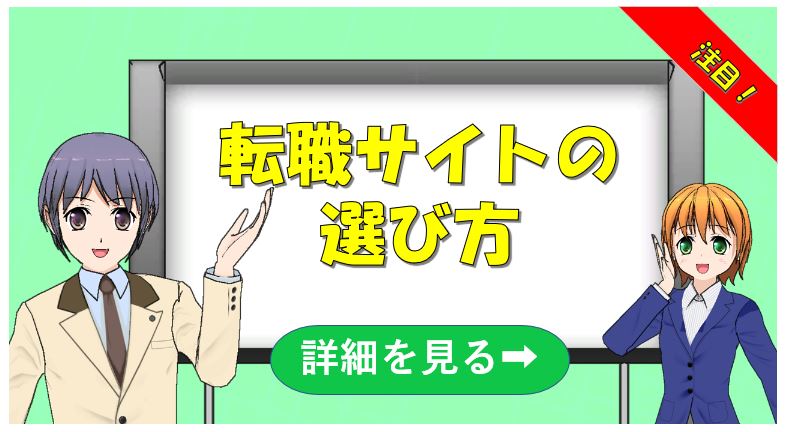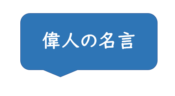部下の突然の退職申告にどう向き合う?ベストな上司の行動とは

部下から突然の「退職させてください」という申し出を受けたとき、上司としてどのように対応すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
驚きとショックの中でも、冷静な対応は職場の信頼関係を保ち、円満な退職を実現するための重要な鍵です。
この記事では、部下の退職を受けた際の具体的な行動ポイントや、残るメンバーへの配慮、さらには退職予備軍を減らすためのコツをご紹介します。これを参考に、突然の状況にも前向きに対処していきましょう。
目次
退職理由を引き出すコツ:部下との信頼を築く対話術

部下や同僚など、人は会社を辞めていくものです。
しかし、これまで一緒に仕事をしていた部下や同僚から退職の意思を聞いた際はやはり寂しいものです。
まずは退職理由を聞き、本人の気持ちに寄り添うことが大切です。
退職は言いにくいもの
部下は上司に退職の話をする際、「言いにくい」「けど自分で言うもの」「本当の理由を言うべきか」など様々な葛藤をもっています。
ただ、多くの場合は「退職理由を聞いてほしい」「否定せず、ただ自分の話を最後まで聞いてほしい」と考えています。
よくある部下の退職理由
一般的な退職理由では以下のような理由があります。
- 人間関係にストレス
- 給料に不満
- 仕事内容が合わない
- 社風が合わない
- 親の介護・病気
- ノルマ
- 残業
人間関係が退職理由として一番多いと言われていますが、その場合上司にも言いにくくて隠すことも多いです。
そんなときに大事なのが、部下の言葉を否定せず、ただ「ゆっくり頷く」「自分の話より相手の話を聞く」ということ。また、場合によっては自身の失敗談や辛かった経験を話すことも有効です。
誠実な言葉は部下に伝わる
退職理由を話す際には、部下もかなり傷ついていたり、精神的にもぎりぎりのことが多いです。
そして、上司や先輩を課題評価し、この人たちは自分にはできない、何でもできる人と思っていることも多いです。
しかし上司も人間です。むしろたくさんの失敗をしているからこそ今の地位にいるわけなので、これまでの失敗や、「あなただけに話す」という本音を話すことで、部下も心を開いて本当の退職理由を話してくれます。
ショックを受けた上司へ:部下の退職を円満に進めるための指南書

上司から部下へかける言葉や方向には大きく2種類あります。
一つ目は引き止め、会社に残ってもらう方法。
そして二つ目は退職を受容し、引継ぎなど他の社員を守ることです。
上司としてはとても寂しいものですが、どちらも重要な役割です。
引きと止める:優秀な人材と伝える
まずは部下がこれまで行っていた実績や工夫、努力など評価しましょう。
振り返ることで、部下も自信を取り戻したり、もう少し頑張ってみようとやる気になります。
また、「〇〇の仕事は君にしかできない」「実はゆくゆくは〇〇など重要案件も任せる予定だった」という言葉もとても嬉しいものです。
悪口や批判をしない
一番いけないのは
という批判です。
場合によっては言いたくなることはあるかと思いますがお互いしんどくなるだけなので控えましょう。
退職の受け入れ
引き止めも難しく、退職の意思が固い場合は上司や先輩が何を言っても変わらないものです。
場合によっては次の転職先が決まっていたり、決まっていなくても案件がある場合もあります。
そのような場合は円満退職する方向に努め、今いる社員を守るために引き継ぎの話をする必要があります。
会社に残るメンバーのために:退職者への引き継ぎのスムーズな方法

退職者がスムーズに引き継ぎを行うことで、残るメンバーの負担を軽減し、業務の連続性を保つことができます。退職者との最良の関係を維持しながら、チーム全体が前向きに次のステップへ進むための秘訣もお伝えします。
引継ぎの内容を具体的に伝える
例えば対象者が一人で担っていた業務があれば、優先的に引継ぎが必要です。
「誰に」「いつまでに」「どのように」引き継ぐか、具体的に説明しましょう。中には引継ぎに1週間以上かかる場合もありますので、先手を打って早めに伝えましょう。
データの管理
パソコンを使用している場合、全て削除して本部に返却することも多いです。一度削除すると分からなくなるので、必要なデータはUSBか共有フォルダ、または引継ぎ先の社員に渡すようにしましょう。
引継ぎ先の明確化
業務を誰が引き継ぐのか、必ず指示しましょう。部下たちが何となくやると思っていると、実は上司が思っているほど自分では動かず、人任せにしていまいます。しかし、誰が引き継ぐかを明確にするだけで、自発的に動くようになります。
退職の流れを説明
有給は使用できるのか、具体的に何日に退職するのかなど、退職者はとても知りたいと思っています。この点は必ず説明しましょう。また、同僚にどのタイミングで伝えるかも事前に打ち合わせることで円満退職に繋がります。
また、離職票や社会保険、退職届についても説明すると丁寧です。
部下の突然の退職に対応する:上司が知るべき必須アクションガイド

仕事の采配
部下が退職する際、引継ぎだけでなく、業務の割り振りを再度考える必要があります。慣れていた人が行う時間と、初めて行う人の作業時間は大幅に変わります。また、新しく引きついた人に負担がかかりすぎると、さらに退職者が増える懸念があります。
人員補充
退職者が残業や業務過多ということもよくある退職理由です。その場合根本的な見直しも必要なため、人事などに人員補充の相談が必要です。
送別会は本人の意思確認
部下は送別会を望んでいるでしょうか・・・。
人によっては「送別会は当然」という人もいれば「そんなものは必要ない」と考える人もいるでしょう。
ですが、ここは本人に聞いてみることをおすすめします。
送別会を希望するのであれば、少なくてもあなたや同じ部署との人間関係にストレスは抱えていないことが分かります。
逆に本人が送別会などはせず、次の転職先へ気持ちを入れ替えたい可能性もあります。
人間関係や業務の改善で退職予備軍を防ぐには?実践的ヒント集
以下にまとめましたので、今後の退職者を増やさないように予防しましょう。
1. 信頼関係を深めるコミュニケーション
- 定期的な1on1ミーティングを実施し、部下の不安や悩みを聞く場を設ける。
- 小さな成果や努力を認め、感謝の言葉を積極的に伝える。
- 自分の考えや感情を適度に共有し、相互理解を促進する。
2. 職場環境の改善
- ストレスチェックの導入や結果に基づく職場環境の見直しを行う。
- フレックスタイムや在宅勤務を活用し、働きやすい環境を提供する。
- 人間関係を円滑にするためのチームビルディング活動を定期的に行う。
3. 業務負担の公平
- 各メンバーの業務量を見直し、過重労働を防ぐ仕組みを作る。
- タスク分担の透明性を確保し、誰かに偏りすぎないよう工夫する。
- 必要に応じて人員補充や外部リソースの活用を検討する。
4. キャリアアップの支援
- キャリアパスやスキルアップのための研修やセミナーを提供する。
- 部下の強みを活かせるプロジェクトへのアサインを増やす。
- 定期的なフィードバックで成長をサポートする。
5. 離職予備軍の早期発見と対応
- アンケートや面談で、チーム内の不満や課題を見える化する。
- 「感謝が足りない」「孤独感」などの退職リスクサインに注意を払う。
- 解決策が見つからないときは、早めに上司や専門家に相談する。
まとめ
この記事では、部下の退職をめぐるさまざまなシナリオと、その対処法についてお話しました。
退職の申し出は、上司として大きな衝撃を受けるものですが、冷静に対応し、引き継ぎやチーム内の信頼構築に注力することで、職場全体の健全性を保つことができます。
大切なのは、辞める人への温かい対応と、残るメンバーへの配慮の両立です。
これが次の成功へつながる大切な一歩となります。状況が困難なときこそ、上司としての力を発揮し、より良いチーム作りを目指していきましょう。